エンタメ業界を目指すなら知っておきたい「業界用語」集

エンタメ業界に興味があるけれど、「専門用語が飛び交っていて何を言っているのかわからない」と不安になった経験はありませんか?
実際、イベントや撮影の現場では、独特の言い回しや略語、独自の言葉づかいが使われることが多く、初めて関わる人にとってはハードルに感じることがあります。
たとえば「バミる」「巻く」「インカム」「ケツカッチン」など、一見意味がわからない言葉が当たり前のように飛び交います。
こうした「業界用語」は、意味を理解しているだけで現場での動きがスムーズになり、スタッフや先輩からの信頼を得やすくなる重要なスキルのひとつです。
本記事では、エンタメ業界を目指す未経験者や転職希望者に向けて、知っておくと安心な業界用語をわかりやすく紹介し、用語理解の大切さや学び方もあわせて解説します。
FNCCでは、こうした業界特有の言葉も、実際の現場を想定した実務講座の中で自然と身につけることができます。ぜひ最後までご覧ください。
エンタメ業界の現場では「業界用語」が飛び交う

エンタメ業界、特にライブ・イベント・映像制作の現場では、独自の専門用語が多く使われています。これらの言葉は、長年の現場経験の中で生まれた、効率的なコミュニケーション手段でもあります。
たとえば、リハーサル中に「バミっといて」と言われて理解できなければ、次の動きに支障が出てしまいます。また、現場は基本的に時間に追われているため、「わかりません」と聞き返す余裕すらない場合もあります。
そのため、現場に入る前に基本的な用語を知っておくことで、スムーズな立ち回りとチームとの連携がとりやすくなり、安心感をもって働くことができます。
「知っている」だけで即戦力と見なされることもあるほど、用語理解は重要です。
初心者が知っておきたい基本の用語(現場系)

まずは、現場で頻繁に使われる代表的な用語をご紹介します。これらはイベント制作・舞台・ライブ運営などの現場で、最初に覚えるべき言葉です。
バミる(バミリ)
→ 舞台上や床に目印のテープを貼ること。立ち位置や機材の配置を示します。
「このマイクスタンド、バミっといて!」といった使い方をします。
巻く(巻き)
→ スケジュールより早めに進めること。「押してる(遅れてる)」の逆の意味。
「巻きでお願いします」は、「時間を短縮して進めよう」の意味です。
押す(押し)
→ スケジュールよりも遅れていること。現場では「今〇分押しです」といったように使われます。
インカム
→ 無線のヘッドセット。現場スタッフが連絡を取り合うために使います。
「インカム通じて指示ください」といった指示が飛びます。
ケツカッチン
→ スケジュールに絶対に遅れられない状況のこと。
「このリハ、ケツカッチンだから時間厳守で」と使われます。
小屋入り
→ スタッフが会場に入って仕込み作業を始めること。
舞台やライブの本番準備の第一歩です。
ゲネプロ(ゲネ)
→ 本番と同じ流れで行う最終リハーサルのこと。
「今日はゲネまでに立ち位置を完璧にしよう」と言われます。
こうした用語は、どの現場でも使われる共通言語です。現場のスピードについていくためには、まずはこれらを押さえておくと安心です。
制作・技術チームで使われる専門用語(音響・照明・映像)

続いて、音響・照明・映像など技術職の現場で頻出する用語を見ていきましょう。これらは専門職でなくても、演出や進行に関わる場合には知っておくと便利です。
PA(ピーエー)
→ 音響を担当する技術者のこと。Public Addressの略。
モニター
→ 演者が自分の声や音を確認するためのスピーカー。
フェーダー
→ ミキサーの音量調整レバーのこと。「フェーダー上げてください」=音量を上げて、という意味。
明かり(あかり)
→ 照明のこと。「明かりチェンジ」「明かりのキュー」など演出と密接に関係します。
キュー(Cue)
→ タイミングの合図。音や照明、動作を指示するための言葉。「キュー出し」は指示を出すことです。
スイッチャー
→ 複数のカメラ映像を切り替える映像機材、またはその操作担当。
ワイヤレス
→ ケーブルのないマイクやインカムなど。「ワイヤレスの電池切れてない?」などと確認されます。
制作や技術スタッフと関わる仕事を希望する場合、こうした専門用語を知っておくことで、技術的な指示にも迅速に対応できるようになります。
SNS・広報・プロモーション系の用語も押さえておこう

最近では、エンタメ業界の中でもSNS運用やPR、デジタルマーケティングに関わる職種の需要が高まっています。そのため、オンライン発信に関する用語も知っておくと、業務理解が深まりやすくなります。
トンマナ
→ トーン&マナーの略。ビジュアルや文章表現の一貫性を保つための基準。
CTA
→ Call To Actionの略。ユーザーに行動を促す要素(例:「詳細はこちら」ボタンなど)。
エンゲージメント
→ SNSでの「いいね」「シェア」「コメント」など、ユーザーとの反応のこと。
レギュレーション
→ 制作物や投稿内容に関するルール。「この企画、クライアントのレギュレーションに合ってる?」といった形で確認されます。
SNSや広報職は、文章力だけでなく、「業界で使われるルールや共通言語」への理解も求められる場面が増えています。
実践で使える用語力を身につけるには?

業界用語をただ丸暗記するだけでは、実際の現場で応用することは難しいものです。言葉は「使いながら覚える」ことが最も効果的です。
そのためには、次のような方法が有効です:
- 実際の現場を見学・体験する(イベントスタッフのアルバイトなど)
- 映像作品のメイキングや舞台裏ドキュメンタリーを観る
- 業界人のSNS・YouTube・書籍で「現場の言葉」を耳にする
- 講座や研修で現場形式の演習に参加する
FNCCでは、講座の中で実際の現場を想定したロールプレイや、講師の指示に対する反応練習などを取り入れており、自然と用語が身につく仕組みが整っています。
FNCCなら実践的な用語や会話も講座内で学べる!

「現場で用語がわからなかったらどうしよう…」
「プロっぽく動ける自信がない…」
そんな不安を持つ方にこそ、FNCCの講座はおすすめです。
FNCCでは、ただ知識を詰め込むのではなく、実務的なスキルと“現場で通用する会話力”の両方を身につけられるよう設計されています。
たとえば:
- ライブ運営や映像制作の講座では、インカムを使った指示出し演習
- 映像編集講座では、実際の現場フローと技術者の会話例を再現
- SNSマーケティング講座では、クライアントとの打ち合わせ想定のロールプレイ
これらの学習を通じて、「現場で話が通じる人材」として、一歩抜きん出た存在を目指すことができます。
さらに、受講前の不安や質問は、公式LINEでお悩み相談も可能です。「エンタメ業界の仕事についてもっと知りたい」「自分に向いている職種がわからない」といった声にも、現役プロデューサーが丁寧に対応しています。
まとめ|業界用語は、現場で信頼されるための“共通言語”
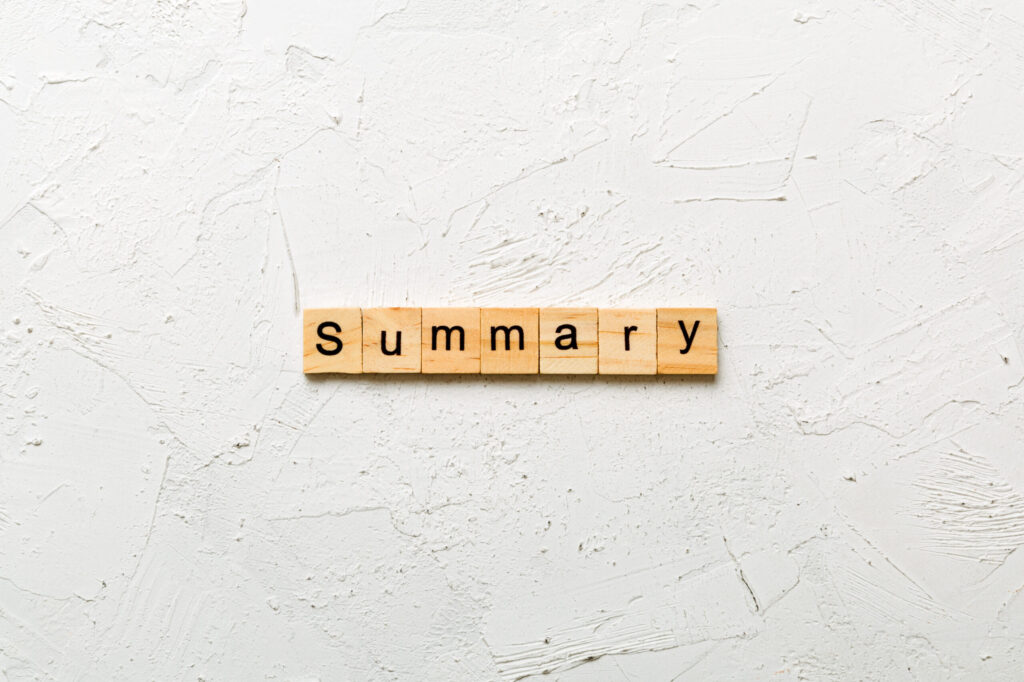
エンタメ業界では、一般的なビジネス用語とは異なる「業界特有の言葉」が日常的に使われています。
こうした用語を理解し、スムーズにやり取りができるようになることで、現場での信頼感や安心感が生まれます。
未経験者でも、準備次第で“通じる人”になることは可能です。
FNCCでは、スキルだけでなく、現場で通用する言葉づかいや対応力までを実践形式で学べる環境が整っています。
「エンタメ業界で働いてみたい」「でも何から始めればいいかわからない」という方は、まずは公式LINEからお気軽にご相談ください。
一緒に、現場で活躍できる自分を目指してみませんか?



